「国富論」を参考にした「機械と製造業の経済」は「経済学原理」や「資本論」で何度も引用されている。人間労働を機械やコンピュータとしてとらえることは何の問題もない。実際に機械の人間化と人間の機械化が進む現在では両者は歩み寄ってきている。コンピュータで現実を再現できるようになってきた現在では、現実がゲーム化してきている。ゲーム化した労働をゲームプレイ・ワーキングと呼ぶ。ゲームプレイ・ワーキングにおいて、労働はどのようなゲームとしても解釈可能であり、「現実」の複数化を加速する。カール・シュミットは敵と味方を区別することを政治の本質とみなした。しかし、複数の現実の中で自我の領域は広がっている。他者は自分がゲームプレイするはずの主体だったかもしれないからだ。
2009/03/05
鈴木(2008)
鈴木健(2008)「ゲームプレイ・ワーキング―新しい労働観とパラレル・ワールドの誕生」東浩紀、北田暁大編『思想地図』vol. 2、日本放送出版協会。
「国富論」を参考にした「機械と製造業の経済」は「経済学原理」や「資本論」で何度も引用されている。人間労働を機械やコンピュータとしてとらえることは何の問題もない。実際に機械の人間化と人間の機械化が進む現在では両者は歩み寄ってきている。コンピュータで現実を再現できるようになってきた現在では、現実がゲーム化してきている。ゲーム化した労働をゲームプレイ・ワーキングと呼ぶ。ゲームプレイ・ワーキングにおいて、労働はどのようなゲームとしても解釈可能であり、「現実」の複数化を加速する。カール・シュミットは敵と味方を区別することを政治の本質とみなした。しかし、複数の現実の中で自我の領域は広がっている。他者は自分がゲームプレイするはずの主体だったかもしれないからだ。
「国富論」を参考にした「機械と製造業の経済」は「経済学原理」や「資本論」で何度も引用されている。人間労働を機械やコンピュータとしてとらえることは何の問題もない。実際に機械の人間化と人間の機械化が進む現在では両者は歩み寄ってきている。コンピュータで現実を再現できるようになってきた現在では、現実がゲーム化してきている。ゲーム化した労働をゲームプレイ・ワーキングと呼ぶ。ゲームプレイ・ワーキングにおいて、労働はどのようなゲームとしても解釈可能であり、「現実」の複数化を加速する。カール・シュミットは敵と味方を区別することを政治の本質とみなした。しかし、複数の現実の中で自我の領域は広がっている。他者は自分がゲームプレイするはずの主体だったかもしれないからだ。
本田(2008)
本田由紀(2008)「毀れた循環―戦後日本型モデルへの弔辞」東浩紀、北田暁大編『思想地図』vol. 2、日本放送出版協会。
戦後日本型循環モデルとは、会社と学校と家庭という三角形である。会社には正社員、非正社員、自営等が属し、家庭に属している「父」が働き、賃金を分配している。学校には、家庭の教育意欲に応えてつつ教育費を徴収し、「子」を労働力として会社に供給する。家庭には「母」「父」「子」がおり、主体的存在となっているのは「母」である。政府は会社に向けて産業政策さえすればよい。
しかし、共働きとなり、主体的存在であった「母」の役割が変わった。そして、会社では正社員や非正社員が多様化し、三角形に属さない「個人」が生まれた。戦後日本型循環モデルには、現状、ほころびが発生している。維持は不可能である。
リチャード・セネットは新しい資本主義への対抗手段を挙げている。いわば機械化する人間活動に残される人間味である。
-物語性(narrative)
全体の時間の中に現在の経験を位置づけること。
-有用性(usefulness)
献身的活動が認められること。
-職人技(craftmanship)
自らの仕事に対する誇りにこだわること。
これらの3点を新しい世代に指し示す必要がある。家庭ではなく、市民や政治がその担い手となるというのもひとつの手ではある。
戦後日本型循環モデルとは、会社と学校と家庭という三角形である。会社には正社員、非正社員、自営等が属し、家庭に属している「父」が働き、賃金を分配している。学校には、家庭の教育意欲に応えてつつ教育費を徴収し、「子」を労働力として会社に供給する。家庭には「母」「父」「子」がおり、主体的存在となっているのは「母」である。政府は会社に向けて産業政策さえすればよい。
しかし、共働きとなり、主体的存在であった「母」の役割が変わった。そして、会社では正社員や非正社員が多様化し、三角形に属さない「個人」が生まれた。戦後日本型循環モデルには、現状、ほころびが発生している。維持は不可能である。
リチャード・セネットは新しい資本主義への対抗手段を挙げている。いわば機械化する人間活動に残される人間味である。
-物語性(narrative)
全体の時間の中に現在の経験を位置づけること。
-有用性(usefulness)
献身的活動が認められること。
-職人技(craftmanship)
自らの仕事に対する誇りにこだわること。
これらの3点を新しい世代に指し示す必要がある。家庭ではなく、市民や政治がその担い手となるというのもひとつの手ではある。
大竹(2009)
大竹文雄(2009)「労働経済学研究に求められるもの」『日本労働研究雑誌』2009年2・3月号(No.584)。
経済学を経済政策へと落とし込むことは、最新の経済現象を追いかけることが一見して良いかもしれない。しかし、万物の流転は研究よりも早く、実証データを正確に分析しつつ追いついていくことはとても気力が必要である。政策研究にとって必要なのは、むしろ質の高い様々な研究を普段から行なうということである。それでこそ、しっかりした学問的裏付けを自信として政策を分析することができる。
経済学を経済政策へと落とし込むことは、最新の経済現象を追いかけることが一見して良いかもしれない。しかし、万物の流転は研究よりも早く、実証データを正確に分析しつつ追いついていくことはとても気力が必要である。政策研究にとって必要なのは、むしろ質の高い様々な研究を普段から行なうということである。それでこそ、しっかりした学問的裏付けを自信として政策を分析することができる。
2009/03/04
Obsfeld and Rogoff (1995)編集中
Obstfeld,Maurice and Kenneth Rogo
ff (1995) "Exchange Rate Dynamics Redux," The Journal of
Political Economy, Vol. 103, pp. 624-660.
あとで読む。
http://d.hatena.ne.jp/eliya/20090304/1236153873
Political Economy, Vol. 103, pp. 624-660.
あとで読む。
http://d.hatena.ne.jp/eliya/20090304/1236153873
クルグマン(2000)
ポール・クルグマン(2000)『良い経済学 悪い経済学』山岡洋一訳、日本経済新聞社。
レスター・サローやロバート・ライシュといった経済学者は日本でも有名だが、クルグマンはこれらの経済学者に好意的でないようだ。クルグマンの立場としては、企業レベルでは競争はあるかもしれないが、国家レベルではプラスサムなので、国家の競争力という概念を否定する。おそらく、サローやライシュは国家同士が市場を浸食しあっていることを描写していたのだろう。だいぶ前に図書館で借りただけなので、内容はほとんど忘れてしまったが、おそらくクルグマンなりに国際経済を解説していた気がする。とにかく、戦略的貿易政策が諸悪の元凶なのだ。
http://d.hatena.ne.jp/kuma_asset/20090301/1235913189
レスター・サローやロバート・ライシュといった経済学者は日本でも有名だが、クルグマンはこれらの経済学者に好意的でないようだ。クルグマンの立場としては、企業レベルでは競争はあるかもしれないが、国家レベルではプラスサムなので、国家の競争力という概念を否定する。おそらく、サローやライシュは国家同士が市場を浸食しあっていることを描写していたのだろう。だいぶ前に図書館で借りただけなので、内容はほとんど忘れてしまったが、おそらくクルグマンなりに国際経済を解説していた気がする。とにかく、戦略的貿易政策が諸悪の元凶なのだ。
http://d.hatena.ne.jp/kuma_asset/20090301/1235913189
2009/03/03
松原(2008)
松原望(2008)『入門ベイズ統計―意思決定の理論と発展』東京図書。
確率は以下のように定義される。
標本空間 の任意の可測事象
の任意の可測事象 に対し実数
に対し実数) を対応させる関数で、3つの公理をみたす。
を対応させる関数で、3つの公理をみたす。
(1)任意の可測事象 に対し、
に対し、\geq 0)
(2)=1)
(3)可測事象 が互いに排反ならば
が互いに排反ならば
=\sum_{i=1}^{\infty}P(E_i))
である。
条件付き確率の定義
=\frac{P(A\cap B)}{P(B)})
 の分割
の分割 が与えられたとき、ベイズの定理が以下のように表現できる。
が与えられたとき、ベイズの定理が以下のように表現できる。
=\frac{P(H_i)\cdot P(A|H_i)}{\sum_{j=1}^{^k} P(H_j)\cdot P(A|H_j)})
ここで、 を原因とすれば、
を原因とすれば、) は結果に対する原因の確率であり、これを原因
は結果に対する原因の確率であり、これを原因 の事後確率と呼ぶ。これに対して、
の事後確率と呼ぶ。これに対して、) を事前確率と呼ぶ。ベイズ統計学では、事前確率が客観的データに基づかなくてもこれを許容し、何かしらの直観や期待に基づいてもよい。これを主観確率あるいは個人確率と呼ぶ。
を事前確率と呼ぶ。ベイズ統計学では、事前確率が客観的データに基づかなくてもこれを許容し、何かしらの直観や期待に基づいてもよい。これを主観確率あるいは個人確率と呼ぶ。
事前確率と事後確率が同じ性質の場合、観測の繰り返しの中で、事後確率は新たな主観確率となる。事後確率の結果から事前確率を更新することをベイズ更新(Bayesian Updating)と呼ぶ。ベイズ更新の分野としてはカルマンフィルターなどがある。
ベイズの定理から\propto w(\theta)\cdot p(z|\theta)) すなわち「事後情報=事前情報×尤度」という関係が導ける。事後情報が観測できるとき、事前情報を特定する作業をベイズ決定という。結果
すなわち「事後情報=事前情報×尤度」という関係が導ける。事後情報が観測できるとき、事前情報を特定する作業をベイズ決定という。結果 からまず推定できるのは確率変数
からまず推定できるのは確率変数 の確率分布であり、これを原因
の確率分布であり、これを原因 としてうまく決定したいのである。
としてうまく決定したいのである。
(1) の確率分布を扱いやすい性質、たとえばベータ分布などと仮定する。
の確率分布を扱いやすい性質、たとえばベータ分布などと仮定する。
(2)結果 の観測から、分布のパラメータ(平均や分散など)を推定する。
の観測から、分布のパラメータ(平均や分散など)を推定する。
(3)損失関数) を最小化する
を最小化する を選ぶ。
を選ぶ。
以上のステップを踏めばベイズ決定ができる。損失関数の性質によって、メジアンもモードも単純平均も推定値となりうる。
先述のカルマンフィルターについては、観測可能な時系列データ から状態(state)
から状態(state) を推定することが目的である。状態空間表現(state space representation)は観測方程式とシステム方程式から構成されている。
を推定することが目的である。状態空間表現(state space representation)は観測方程式とシステム方程式から構成されている。
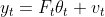

観測方程式の誤差項は観測誤差(observation error)である。ここで新たな観測結果を得たときに状態の推定値を更新していきたいのである。簡単に書けば次のように表現できる。あとは観測情報によるイノベーションを組み込むだけである。

ところでサンプルの少なさから事前情報を抽象的に表わすほかないときには、少ないサンプルからでも事前情報を推定しなければならない場合がある。そういうときには経験的ベイズ決定(empirical Bayes estimation)が有用である。
}{f(x|\theta)}=a(x)+b(x)\theta)
の形をした離散型確率分布) を考える。このとき、
を考える。このとき、) の期待値
の期待値) の経験的ベイズ推定は
の経験的ベイズ推定は
}{b(x)f_n(x)}-\frac{a(x)}{b(x)})
で与えられる。
確率は以下のように定義される。
標本空間
(1)任意の可測事象
(2)
(3)可測事象
である。
条件付き確率の定義
ここで、
事前確率と事後確率が同じ性質の場合、観測の繰り返しの中で、事後確率は新たな主観確率となる。事後確率の結果から事前確率を更新することをベイズ更新(Bayesian Updating)と呼ぶ。ベイズ更新の分野としてはカルマンフィルターなどがある。
ベイズの定理から
(1)
(2)結果
(3)損失関数
以上のステップを踏めばベイズ決定ができる。損失関数の性質によって、メジアンもモードも単純平均も推定値となりうる。
先述のカルマンフィルターについては、観測可能な時系列データ
観測方程式の誤差項は観測誤差(observation error)である。ここで新たな観測結果を得たときに状態の推定値を更新していきたいのである。簡単に書けば次のように表現できる。あとは観測情報によるイノベーションを組み込むだけである。
ところでサンプルの少なさから事前情報を抽象的に表わすほかないときには、少ないサンプルからでも事前情報を推定しなければならない場合がある。そういうときには経験的ベイズ決定(empirical Bayes estimation)が有用である。
の形をした離散型確率分布
で与えられる。
ガードナー(2005)
ハワード・ガードナー(2005)『リーダーなら、人の心を変えなさい。』朝倉和子訳、ランダムハウス講談社。
図書館でコーチング論を探していると、この本を見つけたので、邦題を信頼して借りた。しかし、中身はリーダー論ではなく、心の変化を認知心理学からアプローチするものである。最初の数ページをパラパラ読んで、自分には合わない、この本を読んでも使いこなせない、と思った。ハッとして原題を確認すると、「Changing Minds: The Art and Science of Changing Our Own and Other People's Minds」であった。中身はそこまで読んでいないが、販促用の邦題ではないだろうか。
心の変化をとらえるためには、心とは何かということから始める。どうやら心の中はコンテンツというモヤモヤした記憶と、知性という思考の道具で構成されている。どんなコンテンツを持っているのか、どんな知性を持っているのかということは紙に書いたりすれば明確化できる。コンテンツや知性も認知心理学の研究対象ではあるが、この本では「心の変化」を主題とする。では、心の変化をどうやって研究したら良いかと言えば、事例研究なわけだ。心の変化といえばリーダーである。心動かすリーダーが少なくないからだ。しかし、リーダーだからと行って人の心を動かす必要はないし、リーダーでなくても人の心を動かすことはある。自分には経験が足りないので、この本はゴミ箱に投げ捨てる。
図書館でコーチング論を探していると、この本を見つけたので、邦題を信頼して借りた。しかし、中身はリーダー論ではなく、心の変化を認知心理学からアプローチするものである。最初の数ページをパラパラ読んで、自分には合わない、この本を読んでも使いこなせない、と思った。ハッとして原題を確認すると、「Changing Minds: The Art and Science of Changing Our Own and Other People's Minds」であった。中身はそこまで読んでいないが、販促用の邦題ではないだろうか。
心の変化をとらえるためには、心とは何かということから始める。どうやら心の中はコンテンツというモヤモヤした記憶と、知性という思考の道具で構成されている。どんなコンテンツを持っているのか、どんな知性を持っているのかということは紙に書いたりすれば明確化できる。コンテンツや知性も認知心理学の研究対象ではあるが、この本では「心の変化」を主題とする。では、心の変化をどうやって研究したら良いかと言えば、事例研究なわけだ。心の変化といえばリーダーである。心動かすリーダーが少なくないからだ。しかし、リーダーだからと行って人の心を動かす必要はないし、リーダーでなくても人の心を動かすことはある。自分には経験が足りないので、この本はゴミ箱に投げ捨てる。
登録:
投稿 (Atom)